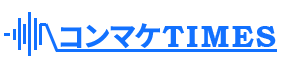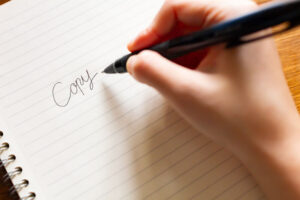「記事を書いても検索順位が上がらない」「何から手をつければいいのか分からない」──こうした悩みを持つWeb担当者は少なくありません。多くの企業が記事作成に苦戦している現場では、共通の課題としてこの声をよく耳にします。
実は、SEOに強い記事作成には明確な手順とルールが存在します。闇雲に書くのではなく、この手順に沿って一つずつ実践していけば、初心者の方でも検索上位を狙える質の高い記事を作成できるようになります。
本記事では、SEOで成果を出すためのオウンドメディア運営のノウハウを基に、記事作成の全工程を8ステップに分けて体系的に解説します。明日からすぐに実践できる具体的な手法や、作業を効率化するツールの活用方法もあわせて紹介しますので、最後までご覧ください。
SEOに強い記事作成とは?まず押さえるべき3つの大原則

具体的な記事作成の手順に入る前に、成果を出すための基本的な考え方を整理しておきましょう。多くの方が「とにかく記事を書けばいい」と考えがちですが、SEOで成果を出すには、これからご紹介する3つの大原則を理解し、常に意識することが不可欠です。
よく見られるのは、専門用語を並べただけの記事や、他サイトの内容を単にまとめただけの記事です。こうした記事は、読者にとっても検索エンジンにとっても価値が低く、上位表示は望めません。以下の3つの原則を守ることで、そうした失敗を回避できます。
原則1:読者の「知りたい」という検索意図に120%応える
SEOの最も重要な核となるのが「検索意図」です。検索意図とは、ユーザーが特定のキーワードで検索する際に抱いている「知りたいこと」「解決したい悩み」を指します。
例えば「記事作成」というキーワードで検索する人は、単に「記事の定義を知りたい」わけではありません。実際には「具体的な書き方の手順を知りたい」「初心者でも分かる方法を教えてほしい」「効率的に記事を作る方法はないか」といった、より具体的なニーズを持っています。
過去の事例として、ある企業のWeb担当者が「SEOツール」というキーワードで記事を書いたものの、検索順位が上がらず悩んでいたケースがあります。記事を拝見すると、ツールの機能説明ばかりで、読者が本当に知りたい「選び方」や「使い分けのポイント」が書かれていませんでした。
検索意図を正しく捉えるには、実際にそのキーワードで検索し、上位表示されているページがどんな情報を、どんな順序で提供しているかを丁寧に分析することが重要です。Googleが上位表示しているということは、それらの記事が多くのユーザーの検索意図を満たしている証拠だからです。
原則2:Googleが内容を理解しやすい構成・構造にする
どれだけ素晴らしい内容を書いても、Googleに正しく理解されなければ意味がありません。検索エンジンは、記事の構造や論理的な流れを重視して評価しています。
具体的には、以下のような構造が重要です。
- 見出しタグ(H1、H2、H3)の正しい階層構造
-
H1タグはページタイトルに1回だけ使用し、H2で大見出し、H3で中見出しというように階層を明確にします。H2の下にいきなりH4を使うような飛び級は避けましょう。
- 各セクションで一貫したテーマを扱う
-
1つのH2セクション内では、そのテーマに関連する情報だけを記載します。話題があちこち飛ぶと、読者もGoogleも内容を理解しづらくなります。
- 結論ファーストの構成
-
各セクションの冒頭で「このセクションで何が分かるか」を明示すると、読者もGoogleも内容を把握しやすくなります。
「面白い文章を書けば読まれるだろう」と考えがちですが、実際には論理的で分かりやすい構造を持つ記事の方が、検索順位が高く、読者の滞在時間も長い傾向があります。読者は求める答えに素早くたどり着きたいと考えているため、明確で整理された記事構造が重要です。
原則3:書き手の専門性・経験・権威性(E-E-A-T)を盛り込む
Googleは近年、E-E-A-T(Experience:経験、Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)を重視した評価を行っています。つまり、「誰が書いたか」「その人はどんな経験を持っているか」が、記事の評価に大きく影響するようになったのです。
例えば、同じ「記事作成の方法」を解説する記事でも、以下の2つでは信頼性が大きく異なります。
- A記事
「記事を書く際は、タイトルと見出しを決めましょう。次に本文を書きます。」 - B記事
「私は過去100社以上のSEOコンサルティングを担当してきましたが、成果の出ない記事には共通点があります。それは『タイトルと見出しが検索意図とズレている』ことです。実際に、あるクライアント様では、見出し構成を見直しただけで検索順位が15位から3位に上昇しました。」
B記事の方が、具体的な経験に基づいた説得力がありますよね。
記事作成では、自身の経験や事例を盛り込むことが重要です。ただ情報をまとめるだけでは、AIが生成した文章との差別化ができません。あなたならではの視点や失敗談、成功事例を加えることで、初めて読者の心に響き、Googleからも評価される記事になるのです。
【完全ガイド】SEO記事作成の全手順を8ステップで徹底解説

ここから本題です。再現性の高い記事作成の全手順を、8つのステップに分けて解説します。
この手順は、多くの企業で成果が出ている実証済みの方法であり、初心者でも迷わず実践できる内容です。各ステップで何を行うべきか、なぜ重要なのか、具体的な進め方を順を追って詳しく説明します。
ステップ1:キーワード選定(読者のニーズを特定する)
記事作成の第一歩は、どのキーワードで上位表示を狙うかを決めることです。このステップを誤ると、どれだけ良い記事を書いても成果に繋がりません。
キーワード選定で重要なのは、以下の3つの観点です。
- 検索ボリューム
-
月間でどれくらい検索されているかを示す指標です。Googleキーワードプランナーやラッコキーワードなどのツールで調べられます。ただし、ボリュームが大きいキーワードは競合も強いため、初心者は月間検索数100〜1,000程度のミドル〜ロングテールキーワードから始めるのがおすすめです。
- 検索意図の明確さ
-
「記事作成」のように、ユーザーが何を求めているか比較的明確なキーワードを選びましょう。「面白い」のような抽象的すぎるキーワードは避けるべきです。
- 自社ビジネスとの関連性
-
検索ボリュームがあっても、自社のサービスや商品と関係のないキーワードでは、成約に繋がりません。
「SEO」のようなビッグキーワードだけを狙うよりも、「中小企業 SEO 始め方」のような具体的なロングテールキーワードで記事を書く方が、早く上位表示されやすく、問い合わせにつながるケースが多くあります。
キーワード選定では、「お宝キーワード」を見つけることが重要です。検索ボリュームがそこそこあり、競合が弱く、自社ビジネスに関連性が高いキーワード──こうしたキーワードを見つけることが、SEO成功の鍵となります。
ステップ2:検索意図の分析(上位記事から答えを学ぶ)
キーワードが決まったら、次はそのキーワードで検索するユーザーが何を求めているかを徹底的に分析します。最も効果的な方法は、実際にGoogleで検索し、上位10位までの記事を丁寧に読み込むことです。
上位記事の分析では、以下のポイントをチェックしましょう。
| 分析項目 | チェックポイント | 目的 |
|---|---|---|
| タイトル | どんな言葉で読者を惹きつけているか | クリックされるタイトルの型を学ぶ |
| 見出し構成 | どんな順序で、どんな情報を提供しているか | 読者が求める情報の全体像を把握 |
| コンテンツの深さ | どこまで詳しく解説しているか | 必要な情報量の目安を知る |
| 独自性 | どんなオリジナル要素があるか | 差別化のヒントを得る |
| 視覚要素 | 図解、表、画像の使い方 | 読みやすさ向上の手法を学ぶ |
例えば「記事作成」で検索すると、上位記事の多くが「具体的な手順」「初心者向けの解説」「効率化ツール」といった要素を含んでいることが分かります。つまり、これらがユーザーの求める情報だということです。
分析作業を怠ると、記事を書いても検索順位が上がらないことがあります。例えば、「SEO対策」というキーワードで、自分の書きたい内容だけをまとめた場合、上位表示は難しくなります。
一方で、上位記事を分析してユーザーが本当に知りたい情報を網羅するように記事を改善すると、数ヶ月で順位が大きく上昇するケースもあります。
競合分析は面倒な作業ですが、ここで手を抜くと後で必ず苦労します。上位記事が提供している情報を漏れなくカバーし、さらにプラスアルファの価値を加える──これが上位表示の絶対条件です。
ステップ3:構成案の作成(記事の骨格=設計図を決める)
分析した内容を基に、記事全体の設計図となる構成案を作成します。構成案とは、タイトルと見出しの一覧のことで、これが記事の骨格となります。
良い構成案の条件は以下の通りです。
- 読者の疑問を漏れなく解消する見出しが揃っている
-
「記事作成とは何か」「なぜ重要か」「具体的な手順」「よくある失敗」など、読者が知りたいであろう情報を網羅します。
- 論理的な流れになっている
-
「基本概念→具体的な手順→応用・注意点」のように、読者が理解しやすい順序で情報を配置します。
- H2、H3の階層が正しく使われている
-
大テーマをH2で、その下位テーマをH3で区切ることで、構造が明確になります。
具体例を挙げましょう。「記事作成」というキーワードの場合、以下のような構成が考えられます。
構成案の例(簡易版)
- H2:SEOに強い記事作成とは?
- H3:検索意図を満たすことの重要性
- H3:構造の最適化
- H3:E-E-A-Tの実践
- H2:記事作成の具体的な8ステップ
- H3:キーワード選定
- H3:検索意図の分析
- (以下、各ステップが続く)
- H2:効率化ツールの紹介
- H2:まとめ
構成案を作る際のコツは、上位記事の見出しをExcelやスプレッドシートに書き出し、共通する要素を抽出することです。10記事分の見出しを並べると、「このテーマではこの情報が必須なんだな」というパターンが見えてきます。
記事作成では、構成案作りに十分な時間をかけることが大切です。構成がしっかりしていれば、本文執筆はスムーズに進みます。
逆に、構成が甘いと何度も書き直すことになり、結果的に時間がかかってしまうのです。
ステップ4:魅力的なタイトルの作り方(クリック率が変わるポイント)
構成案ができたら、次は記事の顔となるタイトルを作ります。検索結果画面で読者の目に最初に入るのがタイトルなので、ここで興味を引けなければクリックされません。
魅力的なタイトルを作る3つのポイントをご紹介します。
ポイント①:目標キーワードを前半に配置する
Googleはタイトル前半の言葉を重視します。また、読者もタイトルを左から右へ読むため、重要なキーワードは前半30文字以内に入れましょう。
良い例:「記事作成の教科書。SEOに強い書き方の手順を初心者へ解説」
悪い例:「初心者でも分かる!プロが教える誰でもできる記事作成の方法」(キーワードが後ろすぎる)
ポイント②:文字数は28〜36文字に収める
タイトルが長すぎると検索結果で「…」と省略されてしまいます。PC版Googleでは約32文字、スマホ版では約36文字まで表示されるため、重要な情報はこの範囲に収めましょう。
ポイント③:読者の興味を引く言葉を入れる
- 具体的な数字
-
「8ステップで解説」「3つのポイント」など、内容の量が分かる数字は効果的です。
- ターゲットの明示
-
「初心者向け」「Web担当者必見」など、誰のための記事かを示します。
- ベネフィットの提示
-
「検索1位を獲得する」「効率化できる」など、読むことで得られるメリットを伝えます。
単に事実を並べるだけでなく、読者が「読みたい!」と思う言葉を加えます。
タイトルを「記事の書き方」から「記事作成の教科書。SEOに強い書き方の手順を初心者へ解説」のように変更すると、クリック率が大きく向上することがあります。タイトルひとつで、読者の反応にこれほど差が出るのです。
ステップ5:本文の書き方(PREP法で論理的に分かりやすく)
構成案とタイトルが決まったら、いよいよ本文を執筆します。ここで活用したいのがPREP法という文章構成の型です。
PREP法とは、以下の頭文字を取ったフレームワークです。
- Point(結論)
- Reason(理由)
- Example(具体例)
- Point(結論の再提示)
この順序で書くことで、論理的で分かりやすい文章を誰でも書けるようになります。
PREP法の実例
悪い例(PREP法を使わない)
「記事を書く際は、キーワードを意識することが大切です。また、見出しを工夫することも重要です。私の経験では、タイトルを工夫すると良い結果が出ました。」
良い例(PREP法を使う)
「記事作成で最も重要なのは、キーワード選定です(結論)。なぜなら、適切なキーワードを選ばないと、どれだけ良い記事を書いても検索結果に表示されないからです(理由)。実際、私が支援したあるクライアント様は、キーワードを見直しただけで検索順位が圏外から5位に上昇しました(具体例)。つまり、成果を出したいなら、まずキーワード選定に時間をかけるべきなのです(結論の再提示)。」
PREP法を使うと、読者は「何が言いたいのか」を素早く理解できます。また、途中で読むのをやめた読者も、冒頭の結論だけで要点を把握できるというメリットがあります。
本文を書く際には、「中学生でも理解できる文章」を意識すると効果的です。専門用語を使う場合は必ず説明を加え、1文は60文字以内にまとめましょう。読者は忙しく、じっくり読む時間がないことを前提に、パッと見て理解できる文章を心がけることが重要です。
ステップ6:装飾・画像挿入のコツ(読みやすさを向上させる)
本文が書けたら、次は装飾と視覚要素の追加です。ただ文字が並んでいるだけの記事は、どれだけ内容が良くても読まれません。読者の離脱を防ぎ、内容の理解を助けるために、以下のテクニックを活用しましょう。
太字・箇条書きの活用
太字(ボールド)
重要なキーワードや結論、数値などを太字にすることで、流し読みしている読者の目に留まります。ただし、使いすぎると逆効果なので、1段落につき1〜2箇所に留めましょう。
箇条書き(リスト)
複数の要素を列挙する際は、箇条書きを使うと一目で理解できます。特に「3つのポイント」「5つの手順」といった内容には必須です。
図解・画像の挿入
文章だけでは伝わりにくい情報は、図解や画像で補いましょう。
フローチャート
手順や流れを示す際に有効です。「ステップ1→ステップ2→…」という流れを視覚化します。
比較表
複数の選択肢やツールを比較する際は、表形式にすると分かりやすくなります。
スクリーンショット
ツールの使い方を説明する際は、実際の画面を載せることで理解度が格段に上がります。
元々テキストのみの記事に図解や表を追加すると、平均滞在時間が大幅に伸びることがあります。読者は必要な情報に素早くアクセスしたいため、分かりやすく整理された記事構造が求められます。
モバイルフレンドリーを意識する
現在、多くのユーザーはスマートフォンで記事を読んでいます。そのため、以下の点に注意しましょう。
- 1段落は3〜4行(150文字程度)で改行
- 画像は横幅800px以下に抑える
- 見出しの後に必ず本文を入れる(見出しの連続は避ける)
装飾は「やりすぎ」に注意が必要です。あくまで読者の理解を助けるためであり、派手にすることが目的ではありません。シンプルで洗練された装飾を心がけましょう。
ステップ7:公開前の最終チェックリスト
記事が完成したら、公開前に必ず最終チェックを行いましょう。公開前に確認すべき項目を、チェックリスト形式で整理すると便利です。
| チェック項目 | 確認内容 | 重要度 |
|---|---|---|
| 誤字脱字チェック | 文章校正ツールで全体を確認 | ★★★ |
| 目標キーワードの配置 | タイトル、H2、冒頭100文字に含まれているか | ★★★ |
| 見出し階層の確認 | H1→H2→H3の順序が正しいか、飛び級はないか | ★★★ |
| リンク切れチェック | 全てのリンクが正しく機能するか | ★★ |
| メタディスクリプション | 検索結果に表示される説明文が設定されているか | ★★ |
| 画像のalt属性 | 全ての画像に代替テキストが設定されているか | ★★ |
| モバイル表示確認 | スマートフォンで見た際に読みやすいか | ★★★ |
| 内部リンク設置 | 関連する自社記事へのリンクが適切に配置されているか | ★★ |
特に重要なのが、誤字脱字のチェックです。信頼性を損なう最大の要因なので、必ず文賢やEnnoといった校正ツールを使って確認しましょう。
書き終えたらすぐに公開する前に、必ずチェックを行うことが重要です。公開前の見直しを怠ると、数値や内容の誤りに気付かず公開してしまう場合があります。
そのため、必ず一晩寝かせてから翌日チェックしたり、制作者とチェック担当者を分けると間違いに気付きやすくなります。時間を置くことで、客観的な視点で記事を見直せるようになるのです。
ステップ8:効果測定とリライト(公開して終わりではない)
記事は公開したら終わりではありません。むしろ、公開してからが本当のスタートです。Googleが記事を評価し、順位が確定するまでには通常3〜6ヶ月かかります。その間、効果を測定し、必要に応じて改善していく「リライト」が重要になります。
効果測定で見るべき指標
Googleサーチコンソールを使って、以下の指標を確認しましょう。
検索順位
目標キーワードで何位に表示されているか。10位以内を目指します。
クリック数(CTR)
検索結果に表示された回数に対して、実際にクリックされた割合。順位が高いのにCTRが低い場合、タイトルやメタディスクリプションを改善します。
表示回数(インプレッション)
検索結果に表示された回数。これが少ない場合、キーワード選定を見直す必要があります。
平均掲載順位
記事全体の平均順位。徐々に上昇していれば良い傾向です。
リライトのタイミングと方法
以下のような場合に、リライトを検討しましょう。
- 検索順位が11〜20位で停滞している
あと一歩で1ページ目に入れる状態です。上位記事と比較して不足している情報を追加しましょう。 - 順位が急落した
Googleのアルゴリズム変更や、競合の台頭が原因です。最新の上位記事を分析し、トレンドに合わせて情報を更新します。 - クリック率が低い
タイトルやメタディスクリプションを魅力的に書き直します。
公開後に検索順位が思うように上がらない記事でも、競合にはない「よくある失敗例」のセクションを追加するなど、リライトによって順位が大きく改善することがあります。リライトは、少しの工夫で大きな成果を生む場合があるのです。
効果測定とリライトを繰り返すことで、記事は徐々に育っていきます。SEOは長期的な取り組みであり、一度の成功で満足せず、継続的に改善していく姿勢が重要です。
記事作成の時間と質を劇的に改善するAIツール「tami-co」

ここまで解説してきた8ステップは、確実に成果を出すために必要不可欠な手順です。しかし正直なところ、特にステップ2の競合分析やステップ3の構成案作成には、慣れないうちは2〜3時間以上かかってしまうことも珍しくありません。
「もっと効率的に、質の高い記事を作れないだろうか──」
記事作成の効率化の重要性は、Web担当者にとってますます高まっています。そこで、AIを活用したSEO記事作成支援ツール「tami-co」を活用する方法があります。
tami-coは、キーワードを入力するだけで、通常2時間以上かかる競合分析をわずか3分で完了し、AIがタイトル・見出し・本文を自動生成してくれる、オールインワンのSEO記事作成支援ツールです。
「tami-co」の7日間無料トライアルで、記事作成の効率化を体験してみませんか?
面倒な競合調査・構成作成をAIが3分で代行
ステップ2とステップ3で解説した、最も時間のかかる競合分析と構成案作成──この2つのプロセスを、tami-coは驚くほど効率化します。
具体的には、以下のような機能が搭載されています。
- 検索意図の自動分析
目標キーワードで検索上位10サイトの構成・共起語・関連語を自動で抽出し、検索者のニーズを可視化します。従来は1サイトずつ手作業で確認していた作業が、ボタン一つで完了するのです。 - 競合の見出し構成を一括取得
上位サイトのH2、H3見出しをドラッグ&ドロップで自分の構成案に取り込めます。「この見出しは使おう」「これは自社にはあまり関係ない」といった判断を、視覚的に行えます。 - AIによる構成案の自動生成
競合分析の結果を基に、AIが最適な見出し構成を提案してくれます。もちろん、提案された構成は自由に編集できるため、自社ならではの独自性を加えることも簡単です。 - キーワードリストの自動提示
サジェストキーワード、関連語、共起語、再検索語(LSI)の4種類のキーワードリストを自動で表示し、記事に盛り込むべき語句を見逃しません。
実際にAIツールを活用すると、従来3時間かかっていた競合分析や構成作成が、わずか数分で完了します。この時間短縮は、特に複数の記事を同時進行で作成しなければならないWeb担当者にとって、大きな助けになるはずです。
SEOのポイントを押さえた本文もAIが下書き
ステップ5の執筆作業も、tami-coのAI機能を使えば大幅に効率化できます。
- 見出し単位での本文自動生成
作成した構成案の各見出しごとに、AIが本文の下書きを生成してくれます。生成された文章はそのまま使えるクオリティですが、もちろん自分の言葉で編集することで、よりオリジナリティの高い記事に仕上げられます。 - キーワードカバー率のリアルタイム表示
執筆中、指定したキーワードがどれだけ含まれているかをリアルタイムで確認できます。不足しているキーワードがハイライトされるため、SEO的に重要な語句の漏れを防げます。 - WordPressへ直接投稿
完成した記事は、tami-coから直接WordPressへ投稿できます。記事の公開プロセス全体が、このツール内で完結するのです。
ただし、ここで一つ重要な注意点があります。AIが生成した文章は、あくまで「下書き」として活用してください。そのまま公開してしまうと、どのサイトも似たような内容になり、差別化ができません。
必ず、あなた自身の経験や事例、独自の視点を加えることで、「あなたにしか書けない記事」に仕上げることが重要です。tami-coは、あなたの記事作成を加速するための「強力な助手」であり、最終的な責任は人間が持つべきなのです。
tami-coで生成した下書きをベースに、自社の事例や顧客の声を追加することで、平均検索順位が大幅な向上が期待できます。AIと人間の協働が、今後の記事作成における効果的なアプローチのひとつなのです。
まとめ:再現性のある手順で、誰でも成果は出せる
ここまで、SEOに強い記事作成の3つの大原則と、具体的な8ステップを詳しく解説してきました。最後に、本記事の要点を簡潔におさらいしましょう。
記事作成の3つの大原則
- 読者の検索意図に120%応える──ユーザーが何を求めているかを徹底的に考える
- Googleが理解しやすい構造にする──見出し階層を正しく使い、論理的な流れを作る
- E-E-A-Tを盛り込む──自分の経験や専門性を活かした独自の視点を加える
記事作成の8ステップ
- キーワード選定──読者のニーズを特定する
- 検索意図の分析──上位記事から学ぶ
- 構成案の作成──記事の設計図を作る
- タイトル作成──クリック率を高める工夫をする
- 本文執筆──PREP法で分かりやすく書く
- 装飾・画像挿入──読みやすさを向上させる
- 最終チェック──誤字脱字や構造を確認する
- 効果測定とリライト──継続的に改善する
記事作成は、決して難しいものではありません。今回ご紹介した正しい手順を、一つずつ丁寧に実践していけば、初心者の方でも必ず成果に繋がります。
成功している企業に共通するのは、正しい手順を守り、継続的に改善を続けることです。一度や二度の失敗で諦めず、PDCAを回しながら改善を続けた企業は、例外なく検索順位を伸ばし、流入数を増やしています。
あなたも今日から、この記事で学んだ手順を実践してみてください。最初は時間がかかるかもしれませんが、繰り返すうちに必ずスピードアップしていきます。そして、効率をさらに高めたい方は、tami-coのようなツールも積極的に活用してみてください。
まずは今日のステップ1「キーワード選定」から始めてみましょう! あなたの記事作成が成功し、検索流入が増えることを心から願っています。