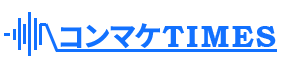「オウンドメディアの記事制作を任されたけれど、何から手をつければいいかわからない……」
「頑張って記事を書いても、なかなか成果(PVやリード)に繋がらない……」
もしあなたが今、このような課題を抱えているなら、きっとお役に立てるはずです。オウンドメディアの運営担当者として、上司やチームから具体的な成果を期待されるプレッシャーは大きいものですよね。
この記事では、特定の企業やサービスに偏らない客観的な第三者の視点から、成果につながるオウンドメディア記事制作の全工程を、明日から実践できる7つの具体的なステップに分解して解説します。
単なる書き方のテクニックだけでなく、企画前の「考え方」から公開後の「改善」まで、一気通貫のノウハウを凝縮しました。この記事を最後まで読めば、あなたは自信を持って、そして効率的に、事業貢献につながる記事を制作するための「型」を身につけることができるでしょう。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
オウンドメディア記事制作で失敗しないための3つの大原則

具体的な制作ステップに入る前に、まず絶対に押さえておくべき3つの大原則についてお話しします。多くの担当者が成果を出せない理由は、この土台となる考え方が抜けているケースがほとんどです。ここを理解するだけで、あなたの記事制作の成功確率は格段に上がります。
1. 読者の検索意図を徹底的に分析する
記事制作の出発点は、常に「読者」です。 なぜ読者はそのキーワードで検索したのでしょうか?その裏側には、読者が解決したい悩みや知りたい情報、すなわち検索意図が隠されています。
検索意図は大きく4種類に分類されます。
- Know(知りたい): 情報を求める意図。「オウンドメディア 記事 書き方」など。
- Go(行きたい): 特定のサイトや場所を探す意図。「Googleアナリティクス ログイン」など。
- Do(したい): 何かを実行したい意図。「記事構成 テンプレート ダウンロード」など。
- Buy(買いたい): 購入を検討している意図。「記事作成 代行 比較」など。
「オウンドメディア 記事制作」というキーワードの主な検索意図は「Know」です。しかし、その背景には「記事制作を効率化したい」「成果を出して社内で評価されたい」といった、読者自身も明確には意識していない潜在的なニーズが隠れています。この潜在ニーズまで汲み取ることで、読者の心に響くコンテンツを作ることができます。Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトでキーワード検索をしてみると、ユーザーの生々しい悩みが見えてくるのでおすすめです。
2. 「誰が」書くか?E-E-A-Tを意識した著者選定
Googleがコンテンツの品質を評価する上で非常に重視しているのが、E-E-A-Tという概念です。 これはExperience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったものです。
簡単に言えば、「その分野の経験や専門性を持つ、信頼できる人が発信している情報か?」が問われるということです。
例えば、あなたが病気について調べる時、匿名のブログ記事と、医師が実名で監修している記事、どちらを信頼しますか?答えは明白ですよね。オウンドメディアの記事も同じです。そのテーマについて語るにふさわしい人物が情報を発信することで、コンテンツの信頼性は飛躍的に高まります。必ずしも著名な専門家である必要はありません。社内の特定分野に詳しいエンジニアや、顧客と日々接している営業担当者など、現場の一次情報を持つ人物こそが最高の書き手になり得るのです。
3. 最終的な成果(KGI)から逆算して企画する
記事制作は、それ自体が目的ではありません。 オウンドメディアを通じて達成したい事業上の最終ゴール、すなわちKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)を明確に設定し、そこから逆算して記事を企画することが不可欠です。
KGIの例:
- サービスへのお問い合わせ件数 月20件
- ホワイトペーパーのダウンロード数 月100件
- 特定商材の売上 月500万円
以前、PVは多いものの全くお問い合わせに繋がらないというメディアがありました。原因は、KGIを意識せず、ただPVを集めやすいキーワードばかりを狙っていたことでした。そこでKGIを「月10件の新規問い合わせ獲得」と再設定し、そこから逆算して「見込み客が検索するであろうキーワード」に絞って記事を制作した結果、3ヶ月で目標を達成できたのです。PVはあくまで中間指標(KPI)であり、最終的な事業貢献を見据えることが成功の鍵です。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
【実践】成果につながるオウンドメディア記事制作7ステップ

ここからは、明日からすぐに使える具体的な記事制作のプロセスを7つのステップで解説します。このセクションを読み終える頃には、あなたが次に何をすべきかが明確になっているはずです。
ステップ1:キーワード選定とペルソナ設定
最初のステップは、どのキーワードで、誰に向けて記事を書くかを決めることです。 ここでのポイントは、検索ボリュームの大きさだけでなく、そのキーワードで検索するユーザーが自社の見込み客になり得るかという視点を持つことです。
キーワード選定には、GoogleキーワードプランナーやUbersuggestといった無料ツールが役立ちます。これらのツールで関連キーワードを洗い出し、以下のように目的別に分類してみましょう。
| キーワードの目的 | 分類の考え方・キーワード例 |
|---|---|
| 集客用キーワード | 認知拡大が目的。検索ボリュームが大きく、潜在層向け。「コンテンツマーケティングとは」など。 |
| リード獲得用キーワード | 課題が明確な層向け。比較・検討段階のキーワード。「記事作成 外注 費用」「MAツール 比較」など。 |
| ナーチャリング用キーワード | 既存顧客や見込み客の育成向け。より専門的なノウハウ。「MAツール 活用事例」など。 |
キーワードが決まったら、そのキーワードで検索する具体的なターゲット読者像(ペルソナ)を設定します。年齢、役職、抱えている課題、情報収集の目的などを詳細に描くことで、記事のメッセージがブレなくなり、読者に「これは自分のための記事だ」と感じてもらえます。
ステップ2:競合分析とコンテンツの切り口決定
次に、狙うキーワードで既に上位表示されている競合の記事を分析します。 ここでの目的は、単に内容を真似ることではありません。競合が提供できていない価値は何か、自社ならどのような独自の切り口を加えられるかを見つけることです。
具体的には、上位10記事ほどを読み込み、以下の点をチェックします。
- どのような情報が網羅されているか?
- どのような読者の疑問に答えているか?
- 不足している情報や、もっと深掘りできる点はないか?
例えば、競合がツールの機能紹介に終始しているなら、自社では「実際の導入事例」や「失敗しないための選定ポイント」といった経験(Experience)に基づいた独自の情報を加えることで、差別化を図ることができます。
ステップ3:読者の疑問を解消する記事構成案の作成
記事の骨子となる構成案(見出し構成)を作成します。 優れた構成案は、読者の思考の流れに沿って、疑問を先回りして解消していくストーリーになっています。
基本的には、まずキーワードに対する直接的な答えを提示し、その後で関連する情報やより深い内容へと展開していくのが論理的です。以下のテンプレートを参考に、見出し(H2、H3)を組み立ててみましょう。
| 見出しレベル | 内容 | テンプレート例 |
|---|---|---|
| タイトル | キーワードを含み、読むメリットがわかる | オウンドメディア記事制作の教科書!成果を出す7ステップ |
| H2 | 読者の大きな疑問・トピック | オウンドメディア記事制作で失敗しないための3つの大原則 |
| H3 | H2の内容を具体的に細分化 | 1. 読者の検索意図を徹底的に分析する |
| H2 | 具体的な方法・手順 | 【実践】成果につながるオウンドメディア記事制作7ステップ |
| H3 | 各ステップの詳細 | ステップ1:キーワード選定とペルソナ設定 |
| H2 | まとめ | まとめ:読者に価値を提供し続けることが成功の鍵 |
この段階で骨子をしっかり固めておくことで、手戻りがなくなり、執筆そのものもスムーズに進みます。
ステップ4:読者を引き込む本文ライティング
構成案ができたら、いよいよ本文の執筆です。 専門的な内容であっても、ペルソナの知識レベルに合わせて、分かりやすい言葉で伝えることを心がけましょう。
ライティングで役立つフレームワークの一つにPREP法があります。
- Point(結論): まず結論を述べる。
- Reason(理由): その結論に至った理由を説明する。
- Example(具体例): 具体例を挙げて理解を深める。
- Point(結論): 最後にもう一度結論を繰り返す。
この型を意識するだけで、文章が格段に論理的で分かりやすくなります。また、専門用語には注釈を入れる、図解や箇条書きを積極的に使うなど、読者がストレスなく読み進められる工夫も重要です。読者の離脱を防ぎ、最後まで読んでもらうことが、結果的にSEO評価にも繋がります。
ステップ5:公開前の最終チェックリスト
記事を書き終えたら、公開前に必ず最終チェックを行いましょう。 いくら内容が良くても、誤字脱字が多かったり、情報が古かったりすると、サイト全体の信頼性を損ないかねません。
以下のチェックリストを活用して、品質を担保しましょう。
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 誤字脱字・表現 | 音読して不自然な点がないか確認する。表記ゆれ(例:Webサイト/ウェブサイト)は統一されているか。 |
| 情報の正確性 | データや引用元の情報は最新か。ファクトチェックは済んでいるか。 |
| SEO設定 | タイトルタグ、メタディスクリプションは設定されているか。画像にalt属性は設定されているか。 |
| リンク | 内部リンク(関連記事へのリンク)は適切に設置されているか。外部リンクがリンク切れになっていないか。 |
| 読みやすさ | スマートフォンで表示した際のレイアウトは崩れていないか。文字装飾は適切か。 |
ステップ6:公開後の効果測定とリライト
記事は公開したら終わりではありません。むしろ、公開してからがスタートです。 定期的に成果を測定し、改善(リライト)していくことで、記事はより強力な資産へと育っていきます。
効果測定には、主に以下の無料ツールを使います。
- Googleアナリティクス: PV数、滞在時間、直帰率など、読者の行動を分析できます。
- Googleサーチコンソール: どのようなキーワードで検索され、表示・クリックされているか、検索順位などを確認できます。
例えば、「表示回数は多いのにクリック率が低い」記事は、タイトルが読者の興味を引けていない可能性があります。その場合はタイトルを修正する。「滞在時間が短い」記事は、導入文で離脱されているか、内容が読者の期待とズレているのかもしれません。データに基づいて仮説を立て、改善を繰り返すことが、継続的に上位表示される記事を育てる上で不可欠です。
ステップ7:継続的な記事メンテナンスと資産化戦略
記事公開後の効果測定とリライトは一度きりで終わりではありません。オウンドメディアの真の価値は、記事を「生きた資産」として育て続けることで生まれます。
まず重要なのは、定期的なメンテナンススケジュールの設定です。公開から1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後と、段階的に記事のパフォーマンスを評価し、必要に応じて改善を加えていきます。特に注目すべきは「検索順位の推移」と「コンバージョンへの貢献度」の2つです。
検索順位が伸び悩んでいる記事については、以下の観点でリライトを検討します。
- 情報の鮮度: 統計データや事例が古くなっていないか確認し、最新の情報にアップデートする
- 網羅性の向上: 上位表示されている競合記事と比較し、不足している情報を追加する
- 内部リンクの最適化: 新しく公開した関連記事へのリンクを追加し、サイト全体の回遊性を高める
一方、検索順位は高いもののコンバージョンに繋がっていない記事は、CTAの配置や文言の見直しが必要です。記事の内容と読者の購買段階に応じて、「無料ダウンロード資料」「ウェビナー申込」「問い合わせ」など、適切なネクストアクションを提示することが重要です。
さらに、季節性のあるキーワードや、トレンドの変化が激しいテーマを扱った記事は、タイミングを見計らった更新が効果的です。例えば「2023年版」といったタイトルの記事は、翌年に「2024年版」として全面的にリニューアルすることで、継続的にトラフィックを獲得できます。
最後に、複数の記事を戦略的に連携させる「コンテンツクラスター」の構築も視野に入れましょう。関連するテーマの記事同士を内部リンクで繋ぎ、特定分野における専門性と網羅性をGoogleにアピールすることで、ドメイン全体のSEO評価向上にも貢献します。このような継続的な改善活動を通じて、一つ一つの記事が相乗効果を生み出し、オウンドメディア全体が強力な集客装置へと成長していくのです。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
記事制作の質と量を両立させるには?内製と外注の判断基準

多くの担当者が直面する課題が「リソース不足」です。高品質な記事を継続的に制作するには、相応の時間と労力がかかります。そこで選択肢となるのが、社内で行う「内製」と、外部のプロに依頼する「外注」です。どちらが良いかは一概には言えず、自社の状況に合わせて判断することが重要です。
| 比較観点 | 内製(社内制作) | 外注(外部委託) |
|---|---|---|
| コスト | 人件費のみ。追加費用は発生しにくい。 | 制作費用が発生する。高品質な記事は高単価になる傾向。 |
| 品質 | 専門知識を持つ人材がいれば高品質を担保できるが、属人化しやすい。 | 専門のライターや編集者が担当するため、安定した品質を期待できる。 |
| スピード | 他業務との兼ね合いで制作ペースが遅くなりがち。 | 契約内容に応じて、スピーディーかつ大量の記事制作が可能。 |
| ノウハウ蓄積 | 制作プロセスを通じて、社内にSEOやライティングのノウハウが蓄積される。 | ノウハウが社内に蓄積されにくい。ただし、良いパートナーなら知見を共有してくれることも。 |
まずは内製でスタートし、ノウハウを蓄積しながら、リソースが足りなくなってきたら一部を外注する、というハイブリッドな形も有効な戦略です。
5,300社超の実績で成果を出す「CROCOの記事作成サービス」
もしあなたが「内製での記事制作に限界を感じている」「よりスピーディーに、確実に成果を出したい」と考えているなら、専門のサービスに外注するのも一つの賢い選択です。
CROCOの記事作成サービスは、これまでに取引社数5,300社超、記事制作数1億本以上という圧倒的な実績を誇ります。豊富な制作実績から蓄積された独自のノウハウを基に、単に記事を制作するだけでなく、戦略設計から公開後の分析・改善まで、貴社のコンテンツマーケティングをワンストップで支援します。
経験豊富な編集者と専門ライターのチームが、貴社のビジネスゴール達成に向けて、成果につながる高品質なコンテンツを継続的に提供します。
自社のオウンドメディアに課題を感じていませんか?豊富な実績を持つプロに、まずは無料で相談してみる(https://cro-co.biz-samurai.com/contact/)
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
まとめ:読者に価値を提供し続けることが成功の鍵
今回は、オウンドメディアの記事制作で成果を出すための考え方と、具体的な7つのステップを解説しました。
最後にもう一度、重要なポイントを振り返ります。
- 失敗しないための3大原則: ①読者の検索意図の分析、②E-E-A-Tの意識、③KGIからの逆算
- 成果を出す7ステップ: ①キーワード・ペルソナ設定 → ②競合分析 → ③構成案作成 → ④ライティング → ⑤最終チェック → ⑥効果測定・リライト→ ⑦継続的な記事メンテナンスと資産化戦略
- リソース問題: 状況に応じて内製と外注を賢く使い分ける
様々なテクニックやフレームワークをご紹介しましたが、最も大切な本質は「一貫して読者の課題解決に寄り添い、価値ある情報を提供し続ける」という姿勢です。この想いこそが、読者の信頼を勝ち取り、Googleに評価され、最終的に事業の成果へと繋がる最も重要な鍵となります。
この記事が、あなたのオウンドメディア運営の一助となれば幸いです。