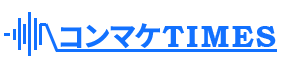企業のオウンドメディア担当者として、あるいはWebライターとして、「今度、顧客インタビューの記事をお願いね」と上司から突然依頼され、何から手をつけていいか途方に暮れていませんか?
「面白い記事を書きたいけど、どうやって話を引き出せばいいんだろう…」
「取材相手に失礼がないか、段取りが不安…」
「そもそも、インタビュー記事ってどういう手順で作成するの?」
これまで数多くのBtoB企業のコンテンツマーケティングを支援し、経営者から社員、お客様まで、様々な方へのインタビュー記事を制作してきました。その経験から断言できるのは、質の高いインタビュー記事は、正しい手順とちょっとしたコツさえ知っていれば、誰でも書けるようになるということです。
この記事では、企画の立て方から取材の作法、読者の心を動かす執筆術、そして公開後のフォローまで、インタビュー記事作成の全手順を、初心者の方にも分かりやすく、網羅的に解説します。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
インタビュー記事作成の全体像と基本フロー

インタビュー記事の作成は、単に話を聞いて文章に起こすだけではありません。成功の鍵は、企画から公開までの一連の流れを理解し、各ステップでやるべきことを着実にこなすことにあります。まずは、この基本となる8つのステップを把握しましょう。

この8ステップを一つひとつ丁寧に進めていくことが、質の高い記事への最短ルートです。それでは、最初のステップから具体的に見ていきましょう。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
【ステップ1】企画・準備編:記事の成否は8割ここで決まる

多くの初心者が取材当日のことに気を取られがちですが、インタビュー記事の品質は、実は取材前の「企画・準備」段階で8割が決まります。ここでの準備が不十分だと、どんなに取材や執筆を頑張っても、的の外れた内容の薄い記事になってしまいます。「何から手をつけていいかわからない」というあなたの不安を解消するため、具体的なタスクを一つずつ解説します。
目的(KGI・KPI)を明確にする:誰に、何を伝え、どうなってほしいか
まず最初に、「なぜ、この記事を作るのか?」という目的を明確にしましょう。目的が曖昧なままでは、誰に何を伝えるべきかが定まりません。採用、ブランディング、販促など、ビジネス上の目的に応じて、記事が達成すべきゴール(KGI/KPI)を設定します。
| 目的 | ターゲット読者(誰に) | 記事で伝えるべき内容(何を) | KGI(最終目標)の例 | KPI(中間指標)の例 |
|---|---|---|---|---|
| 採用強化 | 転職希望者、新卒学生 | 社員の働きがい、キャリアパス、企業文化の魅力 | 採用応募者数の増加 | 採用ページのPV数、記事からのエントリー数 |
| ブランディング | 潜在顧客、業界関係者 | 経営者のビジョン、企業の専門性、開発秘話 | 企業やサービスの認知度向上 | 記事のPV数、SNSでの指名検索数、被リンク獲得数 |
| 商品・サービス販促 | 導入検討中の企業担当者 | 顧客の導入事例、成功体験、具体的な活用法 | リード(見込み客)獲得数の増加 | 記事からの資料請求数、問い合わせ数、ホワイトペーパーDL数 |
このように目的を具体化することで、取材で聞くべきこと、記事で強調すべきことが自ずと見えてきます。
取材対象者のリサーチ:最低限これだけは調べておくべきこと
次に、取材対象者について徹底的にリサーチします。リサーチは、質の高い質問を生み出すための土台であり、相手への敬意の表れでもあります。よくある失敗の一つに、リサーチ不足が原因で、相手が既に何度も語っていることを聞いてしまうことがあります。そうならないためにも、以下の点は必ずチェックしましょう。
- 公式サイト・SNS
- 企業サイト: 事業内容、企業理念、沿革、プレスリリースなど、基本的な情報を網羅的に確認します。
- 個人SNS(Facebook, X, LinkedInなど): 人柄や最近の関心事、専門分野に関する発信などをチェックします。共通の話題が見つかれば、当日のアイスブレイクにも役立ちます。
- 過去のメディア露出
- 過去のインタビュー記事や登壇イベントのレポートを検索し、これまでに何を語ってきたかを把握します。同じ質問を避け、さらに一歩踏み込んだ質問を用意するための重要な手がかりです。
- 関連資料
- 著書や論文、ブログ記事などがあれば、必ず目を通しておきましょう。その人の思考の根幹に触れることができます。
質問項目の作成:相手の本音と物語を引き出す質問のコツ
リサーチで得た情報を基に、質問項目を作成します。ここで重要なのは、単なる事実確認で終わらない、「本音」や「物語」を引き出す質問を用意することです。「うまく話を引き出せるか不安」という方の多くは、ここでつまずきます。良い質問と悪い質問の例を見てみましょう。
- 悪い質問(クローズドクエスチョン): 「はい」「いいえ」で終わってしまう質問。
- 例:「このプロジェクトは大変でしたか?」→「はい、大変でした」
- 良い質問(オープンクエスチョン): 相手が自由に語れる、具体的なエピソードを引き出す質問。
- 例:「このプロジェクトで、特に大変だったのはどのような点ですか?どうやって乗り越えられたのですか?」
相手が思わず語りたくなるような質問を投げかけるのがプロの技です。
- きっかけを問う質問: 「〇〇を始めようと思われた、最初のきっかけは何だったのでしょうか?」
- 具体的なエピソードを問う質問: 「その中で、特に印象に残っているエピソードがあれば教えていただけますか?」
- 価値観や哲学を問う質問: 「〇〇様が仕事をする上で、最も大切にされている価値観は何ですか?」
- 未来を問う質問: 「この事業を通じて、今後どのような世界を実現したいとお考えですか?」
これらの質問を5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して組み合わせ、話の流れを想定しながらリストアップしていきましょう。
取材依頼と事前準備:アポ取りメールの例文と当日の持ち物リスト
質問項目が固まったら、いよいよ取材依頼です。相手は忙しい中、貴重な時間を割いてくれます。失礼のないよう、丁寧な依頼を心がけましょう。
件名:
【取材ご協力のお願い】株式会社〇〇 〇〇様本文:
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇様はじめまして。
突然のご連絡失礼いたします。
私、CROCO株式会社でメディア「△△」の編集を担当しております、〇〇と申します。この度、〇〇様の△△におけるご活躍を拝見し、ぜひ弊社のメディアにて〇〇様のお取り組みやビジョンについてお話を伺いたく、ご連絡いたしました。
つきましては、下記の内容でインタビュー取材のお時間をいただくことは可能でしょうか。
・媒体名: △△(URL: https://…)
・企画趣旨: (例:〇〇業界で活躍するプロフェッショナルの仕事術を通じて、若手ビジネスパーソンにキャリアのヒントを提供する)
・想定読者: (例:20代〜30代のビジネスパーソン)
・インタビュー希望日時:
- 〇月〇日(〇)〇〇:〇〇~〇〇:〇〇
- 〇月〇日(〇)〇〇:〇〇~〇〇:〇〇
- 〇月〇日(〇)〇〇:〇〇~〇〇:〇〇
・所要時間: 60分程度を想定
・場所: 貴社オフィス、またはオンライン
・主な質問内容: (事前に質問の概要を共有すると相手も安心します)- 〇〇事業を立ち上げられた経緯について
- 事業を通じて実現したいビジョンについて
- ご自身のキャリアで大切にされていること
公開前には、〇〇様に原稿をご確認いただくお時間も設けますので、ご安心ください。
ご多忙の折、大変恐縮ではございますが、ご検討いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
アポイントが取れたら、当日の持ち物を準備します。忘れ物がないよう、リストで確認しましょう。
- 必須アイテム
- ICレコーダー: 必ず2台用意し、バックアップを取りましょう。スマートフォンのアプリも予備として役立ちます。
- 筆記用具・メモ帳: 要点や追加の質問をメモするために必須です。
- 名刺: 自分の身分を明かし、信頼を得るための第一歩です。
- 事前に作成した質問リスト
- あると便利なアイテム
- カメラ: 記事に掲載する写真を撮影します。スマートフォンのカメラでも問題ありませんが、一眼レフがあるとより高品質な写真が撮れます。
- 三脚: 手ブレを防ぎ、安定した構図で撮影できます。
- ノートパソコン: その場で追加情報を調べる際に便利です。
【ステップ2】取材当日編:相手に気持ちよく話してもらうための作法

入念な準備を終え、いよいよ取材当日です。ここでの目標は、取材対象者にリラックスしてもらい、気持ちよく話してもらうことです。あなたが緊張していると、その空気は相手にも伝わってしまいます。自信を持って、誠実なコミュニケーションを心がけましょう。
アイスブレイクと自己紹介:取材は名刺交換の瞬間から始まっている
取材は、ICレコーダーの録音ボタンを押す前から始まっています。最初の5分間のアイスブレイクが、その後の9割の空気感を決定づけると言っても過言ではありません。
まずは笑顔で挨拶と自己紹介を行い、取材の機会をいただいたことへの感謝を伝えます。その後、リサーチで見つけた共通の話題や、相手のSNS投稿への感想などを切り口に、雑談から入るのがおすすめです。
- 「〇〇様のFacebookで拝見したのですが、最近△△に行かれたのですね!私も好きで…」
- 「オフィスにいらっしゃる猫、可愛いですね!お名前は何というのですか?」
こうした何気ない会話が相手の心をほぐし、「この人になら話してもいいかな」という安心感に繋がります。
傾聴と相槌、リアクションの重要性
取材中は、あなたが話す時間よりも、相手の話を聞く時間が圧倒的に長いことを意識してください。インタビュアーの最も重要なスキルは「傾聴」です。
- 適切な相槌: 「はい」「ええ」だけでなく、「なるほど!」「そうだったのですね!」「面白いですね!」など、バリエーションを持たせましょう。
- うなずき: 相手の目を見て、深くうなずくことで、「あなたの話を真剣に聞いています」というメッセージが伝わります。
- 驚きや共感の表情: 相手の話の内容に合わせて、表情豊かにリアクションすることも大切です。特にオンライン取材では、普段より少し大きめなリアクションを心がけると、熱意が伝わりやすくなります。
深掘りの技術:「なぜ?」「具体的には?」で話の解像度を上げる
用意した質問を順番にこなすだけでは、表面的な話で終わってしまいます。相手の回答に対して、さらに一歩踏み込む「深掘り」こそが、記事に深みと独自性を与えます。
相手の回答の中に、気になるキーワードやエピソードが出てきたら、すかさず追加の質問を投げかけましょう。
- 相手:「その時は、とにかくがむしゃらに頑張りました」
- あなた:「『がむしゃらに』というのは、具体的にはどのようなことをされたのですか?」
- 相手:「とにかくお客様のところに毎日通って…」
- あなた:「なぜ、そこまでして毎日通おうと思われたのですか?その原動力は何だったのでしょうか?」
このように「なぜ?」「具体的には?」「例えば?」を繰り返すことで、話の解像度が上がり、読者の心を打つ具体的なエピソードが見つかります。
時間管理とクロージング:感謝を伝えて気持ちよく終える
面白い話に夢中になっていると、あっという間に時間は過ぎてしまいます。予定時刻の10分前には、残りの質問数を確認し、クロージングを意識し始めましょう。
最後に、「本日お話しいただいた中で、〇〇様が読者に最も伝えたいことは何でしょうか?」といった質問で、話の核心を再確認するのも有効です。
取材が終わったら、録音を停止し、改めて感謝の言葉を伝えます。「本日は貴重なお話をありがとうございました。おかげさまで素晴らしい記事になりそうです」といった一言が、相手との良好な関係を築きます。今後の流れ(原稿確認の時期など)もこの時に伝えておきましょう。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
【ステップ3】文字起こし・構成案作成編:素材を料理する設計図作り

無事に取材を終えたら、次はオフィスでの作業です。ここからは、取材で得た原石(=音声データ)を、読者が読みやすい記事という宝石に磨き上げていく工程に入ります。面倒に感じる作業も多いですが、ここでの丁寧さが記事のクオリティを大きく左右します。
効率的な文字起こしの方法:AIツール活用のススメ
まずは、録音した音声データをテキスト化する「文字起こし」から始めます。1時間のインタビュー音声を全て手作業で文字起こしすると、4〜5時間はかかると言われています。これは非常に根気のいる作業です。
そこでおすすめしたいのが、AI文字起こしツールの活用です。近年、AIの精度は飛躍的に向上しており、NottaやVrewといったツールを使えば、1時間の音声データも10分程度でテキスト化できます。もちろん誤字脱字の修正は必要ですが、作業時間を劇的に短縮できるため、使わない手はありません。
情報の取捨選択:記事の「幹」となる最重要メッセージを見つける
文字起こしをすると、膨大なテキスト量に圧倒されるかもしれません。しかし、その全てを記事に盛り込む必要はありません。むしろ、情報を詰め込みすぎると、何が言いたいのか分からない散漫な記事になってしまいます。
ここで重要になるのが、ステップ1で設定した「記事の目的」に立ち返ることです。
- この記事で、読者に最も伝えたいメッセージは何か?
- このメッセージを最も象徴しているエピソードはどれか?
- 読者の課題解決に直接繋がらない、削っても良い部分はどこか?
このように、記事の「幹」となる最重要メッセージを決め、そこから枝葉を広げるように情報を整理していくのがコツです。
代表的な3つの記事構成フォーマットと例文
情報の取捨選択ができたら、記事の設計図となる「構成案」を作成します。インタビュー記事には、代表的な3つのフォーマットがあります。それぞれの特徴を理解し、記事の目的や取材対象者のキャラクターに合わせて最適なものを選びましょう。
| フォーマット | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| Q&A形式 | インタビュアーの質問(Q)と、取材対象者の回答(A)を交互に掲載する最もシンプルな形式。 | 読者が知りたいことをピンポイントで探しやすい。初心者でも構成を作りやすい。 | 話の流れが途切れやすく、物語性が生まれにくい。 |
| 一人称語り形式 | 取材対象者が自分自身の言葉で読者に語りかけるように構成する形式。インタビュアーの存在は消す。 | 読者が取材対象者に感情移入しやすく、物語に引き込まれやすい。 | ライターの構成力と文章力が問われる。 |
| ルポ形式 | インタビュアー(三人称視点)が、取材当日の様子や取材対象者の表情、場の雰囲気などを描写しながら話を紹介する形式。 | 臨場感が生まれ、ドキュメンタリーのように読める。取材対象者の人柄を多角的に伝えられる。 | 高度な文章力と客観的な視点が必要。 |
どのフォーマットを選ぶかで、記事の印象は大きく変わります。初心者のうちは、まずQ&A形式から挑戦してみるのがおすすめです。
【ステップ4】執筆編:読者の心を動かす文章術

構成案という設計図が完成したら、いよいよ執筆です。ここからは、読者の心を掴み、最後まで飽きさせずに読ませるためのライティングテクニックが求められます。「読者の心に響く、面白い記事を書きたい」というあなたの想いを、具体的な言葉に乗せていきましょう。
読者の興味を引く魅力的なタイトルの付け方
タイトルは、読者が記事を読むかどうかを決める最も重要な要素です。どんなに本文が素晴らしくても、タイトルが魅力的でなければクリックすらされません。以下の型を参考に、記事の内容を的確に表し、かつ読者の興味を引くタイトルを考えましょう。
- ベネフィット訴求型: 読者が記事を読むことで得られるメリットを提示する。
- 例:「未経験からWebライターに!月収50万円を達成した私の全記録」
- 数字訴求型: 具体的な数字を入れて、インパクトと信頼性を高める。
- 例:「創業3年で売上10億円。急成長を支えた3つの逆転の発想とは」
- ノウハウ型: 〇〇する方法、〇〇のコツなど、具体的な方法論を提示する。
- 例:「【プロ直伝】面白いインタビュー記事の書き方。企画から取材までの5ステップ」
- ターゲット訴求型: 「〇〇なあなたへ」と、特定の読者に呼びかける。
- 例:「初めて部下を持ったあなたへ。チームを成功に導くリーダーの条件」
冒頭で読者の心を掴む「リード文」の書き方
タイトルで興味を持った読者が、次に目にするのが「リード文」です。リード文の役割は、読者の課題に共感し、「この記事は自分のためのものだ!」と思ってもらい、本文へと引き込むことです。
- 共感を示す: 「〇〇で悩んでいませんか?」と読者の悩みを代弁する。
- 問題提起: 読者がまだ気づいていない課題を提示する。
- 記事の要約とベネフィット: この記事で何がわかるのか、読むとどうなれるのかを簡潔に伝える。
この記事の冒頭部分も、このリード文の書き方を意識して作成しています。ぜひ参考にしてみてください。
話し言葉を「読ませる」文章に整えるコツ
文字起こししたテキストは、そのままでは非常に読みにくい「話し言葉」です。これを、読者がスムーズに理解できる「書き言葉」に変換する作業が必要です。
| 話し言葉(Before) | 書き言葉(After) | ポイント |
|---|---|---|
| 「えーっと、やっぱりあのー、一番大事なのは、なんていうか、お客様のこと、ですかね。それをこう、第一に考えるっていうか…」 | 「最も大切にしているのは、お客様第一の精神です。」 | 不要なつなぎ言葉(えーっと、あのー)を削除し、語尾を整えて簡潔にする。 |
| 「そういうのが色々あって、それでまあ、結果的にこのサービスが生まれた、みたいな感じですね。」 | 「様々な課題が浮き彫りになる中で、それらを解決するために本サービスは生まれました。」 | 曖昧な表現を避け、具体的な言葉に置き換える。 |
ただし、全てを完璧な書き言葉にする必要はありません。取材対象者の個性的な言い回しや熱意がこもった言葉は、あえてそのまま残すことで、文章にリズムとリアリティが生まれます。
取材対象者の人柄が伝わる「地の文」の役割
会話文(「」)だけを並べるのではなく、その合間に「地の文」を入れることで、記事はより立体的になります。地の文の役割は、会話だけでは伝わらない情報、特にその場の雰囲気や取材対象者の人柄を伝えることです。
- 表情の描写: 「そう語る〇〇さんの目は、少年のように輝いていた。」
- 仕草の描写: 「一度、天を仰いでから、ゆっくりと当時のことを話し始めた。」
- 背景の補足: 「〇〇さんが指差した先には、創業当時に仲間と作ったという手作りの社訓が飾られていた。」
こうした描写が、読者の想像力を掻き立て、取材対象者への親近感を深めます。
読後感を高める「まとめ」の書き方
記事の最後を締めくくる「まとめ」は、読後感を決定づける重要なパートです。記事全体の要点を簡潔に振り返り、取材対象者が最も伝えたかったであろうメッセージを改めて強調しましょう。
そして、読者が「読んでよかった」「明日から頑張ろう」と思えるような、前向きなメッセージで締めくくるのが理想です。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
【ステップ5】推敲・校正・公開編:記事の品質を最大化する最終工程

素晴らしい記事が書き上がりましたね。しかし、まだ終わりではありません。公開前の最終チェックが、記事の信頼性を担保し、品質をプロのレベルに引き上げます。誤字脱字一つで読者の信頼を失うこともあります。最後まで気を抜かずに、丁寧な仕上げを行いましょう。
音読でチェックする:文章のリズムと誤字脱字
自分で書いた文章は、思い込みで読んでしまうため、間違いに気づきにくいものです。そこでおすすめなのが「音読」です。
声に出して読んでみることで、
- 文章のリズムが悪く、読みにくい箇所
- 誤字脱字や、てにをはの間違い
- 論理的におかしい部分
などを客観的に発見できます。少し恥ずかしいかもしれませんが、効果は絶大ですので、ぜひ試してみてください。
取材対象者への原稿確認依頼:信頼関係を損なわないための注意点
記事を公開する前には、必ず取材対象者に原稿を確認してもらいましょう。これは「ゲラチェック」と呼ばれ、トラブルを避けるために必須の工程です。
- 事実誤認の防止: 日付や役職、固有名詞などに間違いがないかを確認してもらいます。
- 意図の確認: こちらの解釈が、相手の意図とずれていないかを確認してもらいます。
- 信頼関係の構築: 相手の意図を尊重する姿勢を示すことで、良好な関係が続きます。
修正依頼があった場合は、真摯に受け止め、対応しましょう。ただし、記事の趣旨から大きく外れるような修正依頼については、編集意図を丁寧に説明し、代替案を提案することも必要です。
公開後の効果測定と関係構築
記事を公開したら、それで終わりではありません。Google Analyticsなどのツールを使って、PV数や滞在時間、読了率などを測定し、どのような記事が読者に響いたのかを分析しましょう。この分析が、次のコンテンツ制作の貴重なデータとなります。
そして、忘れてはならないのが、取材対象者への報告とお礼です。公開した記事のURLと、読者からの反響(「SNSでこんな良いコメントがありましたよ」など)を合わせて報告することで、相手も喜んでくれます。こうした丁寧なコミュニケーションが、次の取材の機会や、新たな人脈の紹介に繋がっていくのです。
インタビュー記事制作に不安なら、プロに任せるのも一つの手

ここまで、インタビュー記事の作成手順を網羅的に解説してきました。この手順に沿って実践すれば、きっと質の高い記事が作れるはずです。しかし、中には「通常業務が忙しくて、ここまで時間をかけられない…」「もっと戦略的な部分からプロに相談したい」という方もいらっしゃるかもしれません。
そのような場合は、記事作成を専門家にアウトソースするのも有効な選択肢の一つです。
5,300社超の実績「CROCOの記事作成サービス」とは
私たちCROCO株式会社は、これまでに5,300社を超えるお客様のコンテンツマーケティングを支援し、累計1億本以上の記事を制作してきました。
豊富な制作実績で培ったノウハウを基に、単に記事を制作するだけでなく、貴社のビジネスゴール達成から逆算したコンテンツ戦略の設計から、企画、取材、執筆、効果測定までワンストップでサポートします。
インタビュー記事1本から、オウンドメディア全体の運用まで、コンテンツに関するお悩みがあれば、ぜひ一度私たちにご相談ください。
「CROCOの記事作成サービス」について詳しく見てみる(URL: https://cro-co.biz-samurai.com/contact/)
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
まとめ:良いインタビュー記事は、読者と取材対象者への誠実さから生まれる
今回は、インタビュー記事の書き方について、企画・準備から公開後のフォローまで、8つのステップに分けて網羅的に解説しました。
たくさんのテクニックをお伝えしましたが、最後に最も大切なことをお伝えします。それは、読者と取材対象者の双方に対する「誠実さ」です。
- 読者の知りたいことに、どこまでも真摯に向き合う。
- 取材対象者への敬意を忘れず、その人の魅力や想いを最大限に引き出す。
この想いさえあれば、多少文章が拙くても、必ず相手の心に届く記事になります。テクニックは、その想いを届けるための手段にすぎません。
この記事で学んだことを活かして、さっそくインタビューの企画を立ててみましょう。もし専門家のサポートが必要なら、いつでもCROCOにご相談ください。