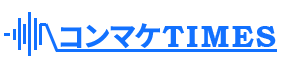「Webサイトのコンテンツを充実させて集客を強化したい。でも、何から手をつければよいか分からない…」
こんな悩みを抱えていませんか?
多くのWeb担当者にとって、特に初心者や他業務と兼任している場合、Webコンテンツ制作の全体像が見えないことが大きな不安になります。
しかし、ご安心ください。コンテンツ制作には確立された手順があり、その流れに沿って進めれば、初心者の方でも必ず成果を出すことができます。
この記事では、成果を出すための7つの手順を、実践的なノウハウとともに詳しく解説します。読み終えるころには、「これなら自分にもできそうだ」という自信と、明日からの具体的な行動計画を手にしていただけるはずです。
そもそもWebコンテンツ制作とは?目的と種類を理解しよう

Webコンテンツ制作とは、インターネット上で公開する情報を企画・作成・発信する一連の活動を指します。文章や画像を用意するだけでなく、読者の課題を解決し、企業のビジネス目標を達成するための戦略的な取り組みです。
BtoBビジネスにおけるWebコンテンツ制作の重要性
BtoB企業にとって、Webコンテンツは営業活動を支える強力な武器となります。具体的には以下のような目的を果たします。
リード獲得
検索エンジンから自社サイトに訪問した見込み顧客に、課題解決のヒントや専門知識を提供することで、問い合わせや資料請求といった具体的なアクションへと導きます。質の高いコンテンツを継続的に発信することで、問い合わせ数を大きく増やすことも可能です。
ブランディング
専門性の高い情報を発信し続けることで、「この分野ならこの会社」という認知を獲得できます。競合との差別化が難しいBtoB市場において、コンテンツを通じた信頼構築は非常に重要です。
顧客育成(ナーチャリング)
すぐに購入・契約に至らない見込み顧客に対しても、定期的に有益な情報を届けることで関係性を維持し、検討が進んだタイミングで選ばれる確率を高めます。
初心者が知っておくべきコンテンツの種類
Webコンテンツには様々な形式がありますが、BtoBビジネスで特に効果的な代表的なものを4つ紹介します。
ブログ記事・コラム
検索エンジンからの流入を獲得する最も基本的なコンテンツです。「〇〇とは」「〇〇の方法」といった検索クエリに対応した記事を作成し、自社の専門知識を提供します。継続的な更新により、サイト全体の評価向上にも繋がります。
導入事例・ケーススタディ
実際の顧客がどのように課題を解決したかを具体的に示すコンテンツです。見込み顧客は「自社と似た企業での成功例」を強く求めており、購買意思決定の最終段階で大きな影響力を持ちます。
ホワイトペーパー・eBook
特定のテーマについて深く掘り下げた資料です。ダウンロード時にメールアドレスなどの情報を取得することで、リード獲得の仕組みとして機能します。専門性の高い内容ほど、質の良いリードを集められる傾向にあります。
動画コンテンツ
製品デモや操作説明、ウェビナーなど、視覚的に情報を伝えるコンテンツです。文字では伝わりにくい複雑な機能や概念を、短時間で効果的に理解してもらえます。
これらのコンテンツは、顧客の購買プロセスの各段階で異なる役割を果たします。認知段階ではブログ記事で見込み顧客を集め、検討段階ではホワイトペーパーで詳細情報を提供し、購買段階では導入事例で最後の一押しをするといった具合です。
【完全ガイド】Webコンテンツ制作の7つの手順と流れ

ここからは、成果に直結するコンテンツ制作の7ステップを詳しく解説します。この流れを理解すれば、「何をすればいいかわからない」という状態から脱却し、具体的な行動計画を立てられるようになります。
STEP1:戦略・企画(何を書くか決める)
すべてのコンテンツ制作は、この戦略・企画フェーズから始まります。ここで方向性を誤ると、どれだけ文章が上手でも成果には繋がりません。「誰に、何を伝え、どのような行動を促すのか」という3つの要素を明確にすることが最重要です。
具体的な目標設定
まず、そのコンテンツで達成したい目標を数値化しましょう。「月間100件の問い合わせを獲得する」「資料ダウンロード数を月50件増やす」といった明確な指標を設定することで、後の効果測定が可能になります。具体的な目標を設定することで、コンテンツの方向性が明確になり、短期間で成果を達成しやすくなります。
ターゲット読者(ペルソナ)の解像度を上げる
「誰に向けて書くか」を明確にすることで、刺さるコンテンツが作れます。ペルソナ設定では以下の要素を具体化しましょう。
- 属性情報
-
役職(部長、課長、担当者)、業種、企業規模、年齢層など
- 課題・悩み
-
日々の業務で困っていること、解決したい問題
- 情報収集行動
-
どのような検索キーワードを使うか、どんな情報源を信頼するか
- 意思決定プロセス
-
一人で決められるのか、上司の承認が必要か
例えば「中小企業のWeb担当者(30代、兼任業務、SEO初心者、上司への報告が必要)」といったように、実在する人物をイメージできるレベルまで具体化してください。
基本的なキーワード選定の考え方
読者が実際に検索するキーワードを選ぶことで、検索エンジンからの流入を獲得できます。初心者の方は、まず以下の3つの視点でキーワードを選びましょう。
- 検索ボリュームの確認
-
月間でどれくらい検索されているかを調べます。Googleキーワードプランナーなどの無料ツールで確認できます
- 競合性のチェック
-
そのキーワードで上位表示されているサイトを確認し、大手企業ばかりでないか、自社でも勝ち目があるかを判断します
- 検索意図の理解
-
そのキーワードで検索する人が何を知りたいのか、何に困っているのかを考えます
例えば「Webコンテンツ制作」というキーワードであれば、検索する人は制作の流れや方法を知りたいと推測できます。この検索意図に応える構成を考えることが、次のステップに繋がります。
STEP2:構成案の作成(記事の設計図を作る)
構成案とは、記事全体の流れを見出しレベルで整理した設計図のことです。いきなり本文を書き始めるのではなく、まず構成案を作ることで論理的で分かりやすい記事になり、執筆時間も大幅に短縮できます。
競合サイトの分析方法 選定したキーワードで実際に検索し、上位10サイトの記事構成を分析しましょう。具体的には以下をチェックします。
- どのような見出し構成になっているか
- どんなトピックが共通して取り上げられているか
- どのような情報が不足しているか
上位サイトに共通して登場する見出しは、読者が求めている情報である可能性が高いため、自社の記事にも盛り込むべきです。一方で、どのサイトも触れていないトピックがあれば、それを追加することで差別化できます。
読者の疑問に答える見出しの立て方 見出しは読者の疑問や関心に対応する形で設定します。例えば以下のような流れを意識しましょう。
- 導入部分
-
読者の課題に共感し、この記事で何が得られるかを示す
- 基礎知識
-
前提となる知識や定義を説明する
- 具体的な方法・手順
-
実践できる情報を段階的に提示する
- よくある質問・注意点
-
読者が疑問に思いそうなポイントを先回りして解説する
- まとめ・次のアクション
-
要点を再確認し、読者が次に取るべき行動を示す
見出しだけを読んで記事の全体像が把握できる状態が理想です。各見出しの下に、どんな内容を書くかのメモ(箇条書きレベルでOK)を残しておくと、執筆がスムーズになります。
STEP3:執筆(伝わる文章を書く)
構成案ができたら、いよいよ本文の執筆です。SEO記事では、専門的な内容を分かりやすく伝えることが何より重要です。
専門用語を避けた分かりやすい文章の書き方 読者の知識レベルを常に意識しましょう。初めて出てくる専門用語には必ず説明を加えます。
- 悪い例 「CVRを改善するためにCTAを最適化しましょう」
- 良い例 「成約率(CVR)を改善するために、行動喚起ボタン(CTA)の文言や配置を最適化しましょう」
また、一文を短く保つことも大切です。一文が60文字を超えると読みにくくなるため、適度に文を区切りましょう。
読者の離脱を防ぐ導入文のポイント 記事の冒頭100文字で読者の心を掴めるかどうかが、その後を読んでもらえるかの分かれ目です。効果的な導入文には以下の要素を含めます。
- 読者の課題への共感 「〇〇でお困りではありませんか?」
- 記事を読むメリット 「この記事では〇〇の方法を具体的に解説します」
- 読後の状態 「読み終えるころには、明日から実践できる知識が身につきます」
導入文を工夫するだけで、記事の読了率や滞在時間を改善することが可能なのです。
PREP法など実践できるライティングの型 PREP法は、説得力のある文章を書くための基本的なフレームワークです。
- P(Point:結論)
-
まず結論を述べる
- R(Reason:理由)
-
その理由や根拠を示す
- E(Example:具体例)
-
事例やデータで裏付ける
- P(Point:結論)
-
再度結論を述べて強調する
例えば「Webコンテンツ制作には戦略が必要です(結論)。なぜなら、目的が不明確なまま作成すると成果に繋がらないからです(理由)。実際に私が支援した企業でも、戦略を明確にした結果、問い合わせ数が3倍になりました(具体例)。だからこそ、まず戦略を立てることが重要なのです(結論)」という流れです。
この型を意識するだけで、初心者の方でも論理的で説得力のある文章が書けるようになります。
STEP4:編集・校正(記事の品質を高める)
執筆後の編集・校正は、記事の品質を最終的に決定する重要なステップです。自分で書いた文章は客観的に見ることが難しいため、必ず時間を置いてから見直すことをお勧めします。
誤字脱字のチェック:基本的なことですが、誤字脱字は読者の信頼を損ないます。以下の点を確認しましょう。
- 同音異義語の誤り(例:「以外」と「意外」、「影響」と「影響」)
- 送り仮名のミス
- 数字の誤り(特に統計データや日付)
Word等の文章校正機能やツールを活用すると効率的です。
第三者視点での読みやすさの確認 :可能であれば、同僚や上司に一度読んでもらいましょう。自分では気づかなかった以下のような問題点が見つかります。
- 論理の飛躍や説明不足の箇所
- 専門用語が多すぎる部分
- 冗長な表現や重複している内容
音声読み上げ機能を使った客観的な推敲方法 :最も効果的な推敲方法の一つが、音声読み上げ機能を使うことです。スマートフォンやPCの読み上げ機能で自分の文章を聞いてみましょう。
- つっかえる箇所は、文が長すぎる可能性がある
- 違和感がある部分は、表現が不自然かもしれない
- 聞いていて眠くなる箇所は、単調で工夫が必要
目で読むだけでは気づかなかった改善点が、耳で聞くことで明確になります。
STEP5:公開と最適化(読者に届ける準備)
質の高い記事ができても、正しく公開・設定しなければ検索エンジンに評価されません。このステップでは、技術的なSEO対策の基本を押さえます。
WordPressなどCMSへの入稿作業 多くの企業サイトで使われているWordPressを例に、入稿時のポイントを説明します。
- 見出しタグ(H2、H3など)を正しく設定する
- 画像には代替テキスト(alt属性)を必ず記入する
- 内部リンクで関連記事を適切に繋ぐ
- カテゴリーやタグを適切に設定する
特に見出しタグは、検索エンジンが記事の構造を理解する重要な要素です。必ず階層構造を守って設定しましょう。
タイトルタグとメタディスクリプションのSEO設定 タイトルタグとメタディスクリプションは、検索結果に表示される部分であり、クリック率に大きく影響します。
- タイトルタグ
-
目標キーワードを含め、32文字以内で魅力的に(長すぎると途中で切れる)
- メタディスクリプション
-
記事の要約を120文字程度で記載し、読者のメリットを明確に
例えば「Webコンテンツ制作の7手順|初心者でも成果を出す完全ガイド」といった形で、キーワードと読者のメリットの両方を盛り込むのが理想的です。
STEP6:分析と改善(コンテンツを育てる)
記事は公開して終わりではありません。データを基に継続的に改善していくことで、検索順位や成果を向上させることができます。
Googleサーチコンソールでの成果分析 Googleサーチコンソール(GSC)は、検索パフォーマンスを分析する必須ツールです。確認すべき主な指標は以下の通りです。
- 表示回数
-
記事が検索結果に表示された回数
- クリック数
-
実際にクリックされた回数
- クリック率(CTR)
-
表示回数に対するクリック数の割合
- 平均掲載順位
-
検索結果での平均的な順位
公開後1〜2週間でデータが蓄積され始めるので、定期的にチェックしましょう。
リライトの判断基準と改善ポイント データを見ながら、以下のような改善(リライト)を行います。
- 表示回数は多いがクリック率が低い場合
-
タイトルやメタディスクリプションを改善する
- 11位〜20位に表示されている場合
-
内容を充実させ、関連キーワードを追加して上位を狙う
- ページ滞在時間が短い場合
-
導入文や構成を見直し、離脱を防ぐ
一般的には、公開後3ヶ月を目安に一度リライトを行うと、順位が大きく改善するケースが多いです。実際に、ある記事では15位から3位まで上昇し、流入数が5倍になりました。
PDCAサイクルでコンテンツを育てる コンテンツ制作は一度作って終わりではなく、継続的な改善サイクルを回すことが重要です。
- Plan(計画)
-
目標設定とキーワード選定
- Do(実行)
-
記事の作成と公開
- Check(評価)
-
データ分析と効果測定
- Action(改善)
-
リライトや新規記事の方向性決定
このサイクルを3ヶ月単位で回すことで、サイト全体のSEO評価が向上し、複数の記事で上位表示を獲得できるようになります。
制作時間を大幅削減。AIツール「tami-co」で執筆を効率化

ここまで解説した7つの手順、特にSTEP1からSTEP3(戦略・企画、構成案作成、執筆)は、専門知識や経験がないと難しいと感じる方も多いでしょう。実際、手順は理解できても、実際に作業を進めると時間がかかってしまう場合があります。
そうした課題を解決するのが、AIライティングツール「tami-co」です。
tami-coが解決する3つの課題
課題1:競合分析に時間がかかる
通常、競合サイト10ページを手作業で分析すると、2時間以上かかります。tami-coでは、キーワードを入力するだけで、わずか3分で上位サイトの見出し構成、共起語、関連キーワードを自動抽出。検索者の意図を可視化します。
課題2:構成案を作るのが難しい
初心者の方が最も苦労するのが、論理的で分かりやすい構成案の作成です。tami-coでは、競合分析の結果を基に、AIが最適な見出し構成を自動生成。ドラッグ&ドロップで簡単に編集もできます。
課題3:執筆スピードが遅い
各見出しごとに、AIが本文の下書きを生成します。そのまま使うこともできますし、ベースとして自分の言葉で編集することで、執筆時間を大幅に短縮できます。
手動作業との比較
| 作業内容 | 手動作業 | tami-co利用時 |
|---|---|---|
| 競合サイト分析 | 約2時間(10サイトを手作業で確認・メモ) | 約3分(キーワード入力のみで自動分析) |
| キーワードリサーチ | 約1時間(関連語・共起語を手作業で収集) | 約1分(4種類のキーワードリストを自動生成) |
| 構成案作成 | 約1時間(見出しを考え、順序を整理) | 約5分(AI提案を確認・調整) |
| タイトル作成 | 約30分(複数案を考え、文字数調整) | 約2分(AI提案+自動採点) |
| 本文執筆(3,000文字) | 約3〜4時間(調査しながら執筆) | 約30分(AI下書きを編集) |
| 合計 | 約7.5〜8.5時間 | 約40分 |
この表が示すように、制作時間を約90%削減できます。
実際の導入成果
コンテンツ制作ツールを活用することで、月に数本しか作成できなかった記事を、安定して10本以上制作できるようになるケースもあります。その結果、数か月後にはオーガニック検索からの流入が大幅に増加し、問い合わせ数の向上につながることもあります。
「何から手をつければ…」と悩む時間をなくしませんか? tami-coの7日間無料トライアルで、効率的なコンテンツ制作を体験してください。
まとめ:今日から始めるWebコンテンツ制作の第一歩
本記事では、Webコンテンツ制作の全体像と、成果を出すための具体的な7つの手順を解説しました。
改めて7つのステップを振り返ります
誰に、何を伝え、どう行動してもらうかを明確にする
競合分析を基に、論理的な記事設計図を作る
分かりやすく、読者の心に響く文章を書く
第三者視点で品質を磨き上げる
技術的なSEO設定を正しく行う
データを基に継続的にコンテンツを育てる
多くの初心者の方が「難しそう」「時間がかかりそう」と感じてしまいますが、この手順に沿って一つずつ進めれば、必ず成果に繋がります。
成功するWebコンテンツ制作に特別な才能は必要ありません。必要なのは、正しい手順の理解と、それを実践する行動力だけです。必要なのは、正しい手順の理解と、それを実践する行動力だけです。
大切なのは、まず最初の一歩を踏み出すことです。完璧を目指す必要はありません。最初は小さく始めて、少しずつ改善していけば良いのです。
この記事で全体像は掴めたはずです。次はあなたの番です。tami-coと一緒に、成果の出るコンテンツ制作を始めましょう!